
Webサイト制作において、「余白」はただのスペースではありません。
ユーザーの印象や行動、そして離脱率にまで関わる、非常に重要な要素です。
なぜ余白が重要なのか?
余白には、以下のような役割があります:余白が持つ5つの力
1. 読みやすさを高める
コンテンツ同士の “区切り” を作ることで、見やすさが大きく変わります。文章の理解がスムーズになります。詰まった文字は、読む前から疲れさせてしまいます。
2. 情報の優先順位を示す
あえて“何も置かない空間”をつくることで、見る人に「ここが大事ですよ」と視線を誘導することができます。つまり、視覚的な強弱=情報設計にもつながります。
3. 高級感・信頼感を与える
余白には「余裕」が宿ります。高級ブランドやIT企業のサイトで余白が多いのはそのためです。空間の使い方ひとつで、ブランドの品格や価格帯さえ想起させることができるのです。
4. 導線を明確にする
情報が詰め込まれすぎたページは、見るだけでストレスに。余白によりがあると、ボタンや重要情報が目立つようになり、迷わず次の行動へ進めます。
5. スマホでの見やすさに直結
狭い画面では余白の効果がさらに顕著です。要素間に十分なスペースがあることで、誤タップを防ぎ、操作しやすくなります。
職種によってサイトの文字数が変わる
製造業や建設業のサイトは比較的文字が多い。
でもさらに多いのは、士業。
これらの共通点は、写真映えしないってこと。
画像が少ないから、どうしても文字数を増やしたくなります。
しかも士業の方は、普段から難解な文章を扱ってるから、大量の活字をストレスに感じない。
それだからか、詰め込みすぎる傾向があります。
例えばプロフィール欄。
ここは経歴の箇条書きで十分。
むしろ、そのほうがわかり易い。
でも、なかには「想い」や「出来事」を書き込まれる方がいます。
文字が多いのが決してダメというわけではありません。
ただ、詰め込んでいい場所とそうでない場所があるんです。
「見映え重視」や「わかり易さ重視」のページもあるということです。
ページによって変わる「余白の役割」
Webサイトでは、すべてのページで同じ余白設計をしてはいけません。
目的や閲覧スタイルによって、余白の“使い方”を変えることが重要です。
トップページ =「魅せる余白」
トップページは、サイト全体の印象を決定づける場所です。
ここでは、「情報の量」よりも「空気感」が求められます。
・キャッチコピーは短く、余白を多めに
・ファーストビューは「読ませる」のではなく「印象で引きつける」
ファーストビューに文字が多すぎると、離脱率が上がる傾向があります。「読むのが大変そう」と判断されるからです
とくにスマホでは、1スクロール目の “圧” が致命的になることも。
また、文字による「情報の量」以上にスペースをとるのが「サイドメニュー」です。
文字の場合、記載の方法によってスペースの調整が可能です。
でも、サイドメニューはスクロールしても常に視界に残り、中央の表示領域を圧迫し続けます。
「大きなスペースを大胆に使う」という今のWebデザインの潮流と相反する存在なのです。
弊社ではテーマを活用してサイト制作を行っていますが、最近のトップページでサイドメニューを持つデザインはほぼ存在しません。
「導線のためにサイドメニューがほしい」とい合われる方もいますが、正直古いです。
サイドメニューでなくてもスマートに設計できます。
リンクやボタンの配置次第で、より洗練された動線を構築できるのです。
そのため、トップページでは余白=引き算の美学。
“伝える情報を絞り込み、あえて空間を残す”ことで、視線の集中と印象操作を行います。
ブログ・情報ページ =「読むための余白」
一方、ブログやコラムなどの情報コンテンツでは、「読むこと」が目的になります。
ここでの余白は “読みやすさ” と “リズム感” を生む設計をします。
・セクションごとの余白で「意味の切れ目」を示す
・見出しや強調表現で、読むペースをコントロール
とはいえ「文字が少ない=優良サイト」というわけではありません。
むしろ、SEO的には一定のボリュームと深さが求められるため、中身のある情報をしっかりと書くことが重要です。
ただし、構造化されていれば “長文でも読まれる”。
余白を使って視線を整理し、「必要な人に必要な情報だけ届く設計」が求められます。
「魅せるページ」と「見せるページ」の切り分け
まとめると、以下のようになります。
| 種類 | 目的 | 役割 |
| 魅せるページ(トップ・LP) | 第一印象・世界観・誘導 | 空気感と導線をつくる |
| 見せるページ(ブログ・FAQ) | 情報提供・悩み解決 | 読みやすさと構造整理 |
この2つは役割がまったく違うため、余白の設計も分ける必要があります。
どちらかに引っ張られすぎると、「デザインは良いのに読みにくい」「情報はあるけど圧迫感がある」といった問題が発生します。
ユーザーが “迷わない” 構造を設計する
もうひとつ大切なのは、すぐに目的地(知りたい情報)に辿り着けるために導線(道案内)
興味のない話を延々と読まされるのは誰もがストレス。
さらに、さんざん読んだ挙句、知りたい情報がないとなれば離脱は確定。
もう2度と来てくれません😢
そうならないためにも、わかり易い導線(道案内)が必要。
でもって、その導線をわかり易くするのも余白なんです。
・詳細情報は「詳しく見る」やアコーディオンなどで段階的に見せる
・グローバルナビや目次で必要な情報にすぐジャンプできるように
興味のないページへの回遊がなくなるため、ストレスがかかりません。
また、文字数が多くても、読みやすいページになります。
つまり、余白は「削る」ためではなく「分ける」ためにあるのです。
まとめ:余白 × 情報設計が、サイトの質を決める
余白は、単なるデザインの美しさだけでなく、
「伝えるべき情報を、誰に、どの順で届けるか」をサポートする大切な要素です。
・読ませるページは、余白で読みやすさを支え
・そして全体は、余白で“迷わない構造”をつくる
「空いている」ではなく「空けている」
それが、洗練されたWebサイトの本質です。
私のサイトに使われている余白が満点とは言いません。
ただ、余白の意味と効果をしっかり意識して、設計していることは間違いありません。
オマケ:オリバーピープルの案内状
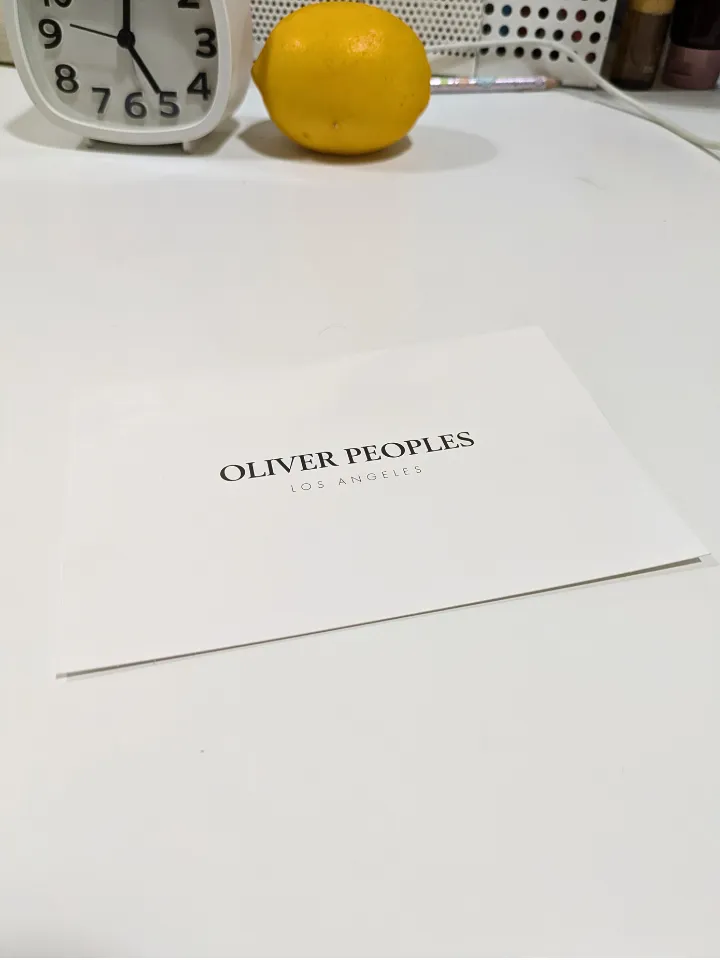
これは購入者に送られるものだから、いまさらブランド説明は不要なんです。とはいえ画像無しはスゴイ!
オリバーピープルに関わらず、一流ブランドはみんなこう。余白がカッコイイですね。